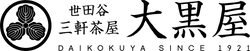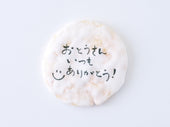「お彼岸だからやってはいけないよ」といわれていることがあるのはご存じでしょうか。
今回は、お彼岸の概要、「お彼岸にやってはいけない」といわれていること7つ、お彼岸にやるべきことについて解説します。
さらに、「お彼岸に土いじりをやってはいけない」は誤解ということ、お彼岸のお供えにおすすめの菓子折りもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
【目次】
お彼岸とは?いつ行われる行事?

まずは、お彼岸とはどんな行事で、いつ行われるものなのかについて解説します。
お彼岸とは
「お彼岸」とは、ご先祖様へ日頃の感謝を込めて供養を行う仏教行事のことです。
この行事の由来は、煩悩のない世界や悟りの世界を表す、仏教用語の「彼岸」といわれています。
もともとお彼岸とは、煩悩がある世界「此岸(この世)」から煩悩のない世界「彼岸(あの世)」へ到達するために、修行する期間を指す言葉だったのです。
現在では、「お彼岸=あの世にいるご先祖様を想いながら日頃の感謝を伝える行事」として定着しています。
ちなみに、お彼岸と混同しやすい「お盆」は、あの世から自宅までご先祖様をお迎えしてご供養する期間です。
時期はいつ?
お彼岸は春と秋の2回にわけて行われる行事であり、日程は以下のように決められています。
- 春彼岸:「春分の日」を中心とした前後3日間
- 秋彼岸:「秋分の日」を中心とした前後3日間
例えば、2025年の秋分の日は9月23日(火・祝)、2026年の春分の日は3月20日(金・祝)なので、この期間中のお彼岸の日程は下記の通りです。
- 2026年の春彼岸:3月17日(火)~3月23日(月)の7日間
- 2025年の秋彼岸:9月20日(土)~9月26日(金)の7日間
「お彼岸にやってはいけない」といわれていること7つ

実は、お彼岸にやってはいけないことは存在しません。
お彼岸は、喪に服すための期間でもなく、仏教の観点からも禁止されていることはないからです。
ただ、お彼岸はご先祖様を供養する期間だからこそ、人によっては下記のようなことを「やってはいけない」と考える場合もあります。
- お宮参りなどの神事
- 結婚式
- 納車
- 引っ越し
- お見舞い
- 水辺で遊ぶこと
- 彼岸花を持ち帰ること
この機会に、上記7つの「お彼岸にやってはいけない」といわれていることを押さえておきましょう。
お宮参りなどの神事
お宮参りとは、無事に出産したことへの感謝や赤ちゃんの成長を願い、住んでいる地域の神様(氏神様)にお参りをする行事です。
このようなお宮参りをはじめ、七五三や安産祈願のように、神様に関する儀式や祭りごとは、仏事と同時に行うべきではないという考えがあります。
神道では「死は穢れ」とされているため、死を扱う仏事と同時に行うのは良くないと感じる方もいるため、時期をずらすなどの配慮を行ってみましょう。
結婚式
結婚式をお彼岸でやってはいけないといわれているのは、「ご先祖様の供養に専念する期間でお祝い事を行うべきではない」とされているからです。
また、お彼岸では、お墓参りなどで参列者の方が忙しくなるため、別日に行うべきという考えもあります。
お彼岸に慶事をすることは禁止されていませんが、気になる方がいる場合はお彼岸の時期を避けることも検討してみましょう。
納車
「喪」の期間に新しいことを始めるのは控えるべきという考えから、お彼岸に納車を行ってはいけないと考える方もいます。
ただ、お彼岸は「喪」の期間ではないので、納車をすることに問題はありません。
引っ越し
引っ越しをお彼岸にやってはいけないといわれているのは、「入居準備などで、お彼岸本来の目的であるご先祖様の供養や修行がないがしろになる」と考えられているためでしょう。
仕事の都合などで引っ越しの時期をずらせない場合は、可能な範囲でご先祖様への供養を行ってみてください。
お見舞い
ご先祖様の供養をするお彼岸だからこそ、お見舞いをすることで「死を連想させる」と考える方もいます。
縁起が悪いということから嫌な気分になってしまう可能性も考慮し、お彼岸にお見舞いをすることは避けた方が良いでしょう。
水辺で遊ぶこと
お彼岸に水辺で遊ぶべきではないといわれている理由は、「供養をされずにさまよう霊が水辺に引き込む」という言い伝えがあるからです。
上記の理由は迷信ですが、特に秋のお彼岸の時期は台風と重なりやすく、水辺の事故が増えやすいため十分注意してください。
彼岸花を持ち帰ること
お彼岸の時期に咲く「彼岸花(ひがんばな)」を持ち帰ることは、「彼岸花を持ち帰ると火事になる」という迷信によって避けるべきとされています。
また、彼岸花はお墓など死に関連する場所で見られることがあるため、不吉と連想する方もいるのです。
一方で、彼岸花は強い毒性を持つため、事故を避けるためにも持ち帰ることは控えましょう。
「お彼岸に土いじりをやってはいけない」は誤解

お彼岸にやってはいけないこととして、草むしりなどの「土いじり」を挙げる方もいますが、これは誤解といえます。
土いじりを控えるべきとされているのは、立春・立夏・立秋・立冬の前にある約18日間の「土用の期間」です。
土用の期間は、土を司る神様が支配する時期と考えられているため、土いじりや基礎工事などの土を動かす作業を避ける風習があります。
お彼岸にやるべきこととは?

お彼岸にやるべきことは、以下の通りです。
- 【事前に行うこと】お仏壇・お仏具の掃除
- お墓参り
- お仏壇のお参りやお供え
- 他家へのお参りやお供え
- お彼岸法要
「お彼岸にやってはいけない」といわれていることと共に、押さえておきましょう。
【事前に行うこと】お仏壇・お仏具の掃除
お彼岸の期間中は、慌ただしく過ごすことも多いので、あらかじめお仏壇・お仏具の掃除をしておくと安心です。
日頃の感謝を込めながら丁寧に掃除をしていきましょう。
お墓参り
お彼岸には、お墓参りをすることも一般的な過ごし方です。
一説によると、「お彼岸はあの世との距離が最も近くなるため、ご先祖様への想いが届きやすくなる」といわれているため、家族でお墓参りをする風習が浸透したとされています。
お彼岸の期間中であればどの日にお墓参りをしても問題ありません。
もし、都合がつかずお墓参りができないときは、無理をせず自宅からご先祖様に手を合わせてみましょう。
お仏壇のお参りやお供え
お彼岸には、お墓参りだけではなくお仏壇のお参りやお供えも行いましょう。
基本的に、お彼岸の初日にお供えをして最終日に下げることが習わしであり、お供え物としてはぼた餅・おはぎ・菓子折りなどが定番です。
他家へのお参りやお供え
地域や場合によっては、お彼岸に他家へのお参りやお供えをすることもあります。
お供え物の定番は菓子折りなどの消えもので、相場は一般的に3,000円〜5,000円程度、初彼岸であれば5,000円〜1万円程度です。
お彼岸法要
地域や家の考え方などによっては、ご先祖様の冥福を祈り、僧侶による読経や参列者による焼香などが行われる「お彼岸法要」が実施されることがあります。
お彼岸法要はお悔やみごとではないので、喪服ではなく紺などの落ち着いた色合いのスーツやワンピースで参加することが基本です。
初彼岸に特別にやるべきことはある?

故人が亡くなってから初めて迎える「初彼岸」に、特別やってはいけないこと・やるべきことはありません。
通常のお彼岸と同じように、ご先祖様に感謝の気持ちを伝え、自分自身を見つめ直す機関として過ごしていきましょう。
お彼岸のお供えにおすすめの菓子折り3選
こちらからは、せんべい・おかき・あられ専門店「三軒茶屋おかきあられの大黒屋」が、お彼岸のお供えにおすすめの菓子折り3選をご紹介します。
- 包みおかき
- 国産有機もち米のあられおかき「四季七彩」
- うすごろも
上記3つのお菓子は個包装されており、お供え物に最適です。
どんなお供え物を用意するべきかお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。
包みおかき

『包みおかき』は、バラエティ豊かな7つの味わいを楽しめるおかきの詰め合わせです。
軽やかな食感とお米の自然な甘みが広がるおかきは、スティック状で食べやすいので幅広い世代の方から人気を集めています。
|
味 |
|
|
賞味期限 |
賞味期限45日以上の商品をお送りいたします。 |
|
価格(税込) |
380g入り:4,320円 |
|
送料(税込) |
|
国産有機もち米のあられおかき「四季七彩」

『国産有機もち米のあられおかき「四季七彩」』は、もち米の横綱とも称される宮城県産の有機「みやこがね」を使用した、あられおかきの詰め合わせです。
醤油や砂糖も有機食品を使用しており、一袋で7種類の深い滋味と美味しさをお楽しみいただけます。
|
味 |
|
|
賞味期限 |
賞味期限45日以上の商品をお送りいたします。 |
|
価格(税込) |
|
|
送料(税込) |
|
うすごろも

『うすごろも』は、ころものように薄く、サクサクと軽やかな口あたりがたまらないうす焼きせんべいの詰め合わせです。
素材の旨みを引き立てた飽きのこない4種類の味わいは、お茶請けとしてもぴったりですよ。
|
味 |
|
|
賞味期限 |
賞味期限60日以上の商品をお送りいたします。 |
|
価格(税込) |
|
|
送料(税込) |
|
まとめ
今回は、お彼岸の概要、「お彼岸にやってはいけない」といわれていること7つ、お彼岸にやるべきことなどについて解説しました。
基本的にお彼岸にやってはいけないことは存在しませんが、仏事に関する考えは人それぞれなので、周りの方への配慮を忘れずに過ごしてみてくださいね。
→メッセージをプリント!『大黒屋のプリントせんべい』はこちらから
【関連記事】